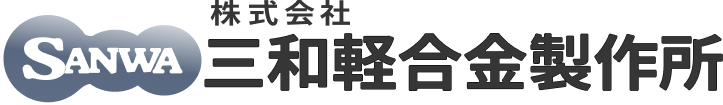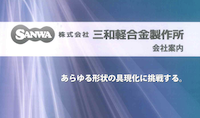鋳物の基礎知識として、設計用語を知っておくことは鋳造を依頼するお客様にとっても有益です。
ご希望の製品を作る上で、その設計が適切かをお客様自身で判断することができます。
※2024/09/28追記・修正
鋳造の基本について知りたい方は、以下の「鋳造とは」の記事を参考にして下さい。
設計用語 目次
- 肉厚
- 抜勾配
- 寸法公差
- 縮み代
- 削り代
鋳物の設計1 肉厚(にくあつ)とは
鋳物の肉厚とは、鋳物の厚みのことです。
肉厚は、鋳物に要求される強度や剛性、耐久性などを満たすことはもちろんですが、鋳造のしやすさも考慮しなければなりません。肉厚が薄すぎると溶湯が鋳型内を流れている途中で冷えて固まり鋳物の形状が不完全になってしまいます。また、肉厚が厚すぎる場合には、凝固にかかる時間が長くなるため金属組織を粗くしたり、内部にひけ巣を発生したりして鋳物の強さを低下させることがあります。
肉厚の均一化
鋳物の肉厚は、できる限り均一で厚さの変化が少ないことが望ましいとされます。これを均肉化といいます。肉厚が不均一で駄肉部があると薄肉部に比べて肉厚部の凝固が遅れ、ひけ巣を発生したり、外部にひけを発生したりします。中子などを用いて均肉化をはかることで、欠陥の発生を回避することができます。鋳物の剛性が必要な場合は、厚肉にするのではなく、リブを使用することで駄肉をなくして剛性を上げることができます。
【まとめ】
鋳物の肉厚は、製品の大きさ、鋳造法、鋳造材料などによって異なりますが、できる限り肉厚差の少ない均一な肉厚とすることで、欠陥の発生を防止できます。
鋳物の設計2 抜勾配(ぬけこうばい)とは
抜勾配は、砂型の鋳型時に鋳型から模型を抜くときや、金型鋳造やダイカストにおいて金型から鋳物を取り出す際に、容易に抜けるようにするために必要な形状を抜く方向に傾斜をつけたものです。抜勾配は、鋳造材料あるいは鋳造方法によって異なり、JIS B 0403:1995(JIS規格では、「抜けこう配」となっていますが、ここでは慣例に従い「抜勾配」と表記します)に規定されています。
抜勾配はどのように設定するか
ロストワックス法やフルモールド法では模型を鋳型から抜くことはないので抜勾配は不要です。しかし、砂型鋳造では鋳型からの模型を取り出す必要があるので模型を引き抜く方向に抜勾配を設定します。抜勾配が不十分だと砂と型との摩擦で砂型が崩れたり、模型が鋳枠の中に残ったりするので、適切な抜勾配をつける必要があります。金型鋳造やダイカストでは、金型から製品を取り出すために取り出し方向にそって製品に抜勾配を設定します。抜勾配が不十分だと製品を取り出す際に、製品が金型にかじりついたり、製品が変形したりすることがあります。
抜勾配は、できる限り大きい方が抜けやすいのですが、大きすぎると勾配の根元と先端との寸法の差が大きくなり、肉厚が指定寸法と異なったり仕上げ代が大きくなったりします。ユーザーからはできる限り小さくすることが望まれるので、十分に協議をして決定します。
【まとめ】
鋳型時に鋳型から模型を抜いたり、金型から鋳物を取り出したりするために、抜く方向に勾配を設けた抜勾配が必要になります。寸法精度と作業性を考慮して適切な抜勾配に設定します。
鋳物の設計3 寸法公差(すんぽうこうさ)とは
鋳物の寸法は、鋳物のできあがり寸法である実寸法と、あらかじめ許された誤差の限界の範囲内である許容寸法があります。
許容寸法は、鋳物に要求される機能を満たし、かつ製造上でもっとも有利なように適当な大小2つの許容限界寸法(最大許容寸法および最小許容寸法)が決められます。この最大・最小許容寸法の差を寸法公差といいます。
【まとめ】
鋳物はさまざまな要因で基準寸法からのいずれを発生します。さまざまな部品として使用するためには、このずれをある範囲に留める必要があります。これが寸法公差です。
鋳物の設計4 縮み代(ちぢみしろ)とは
縮み代とは
鋳型に鋳込まれた溶融金属の温度が低下して室温に至までには、液体収縮、凝固収縮、固体収縮によって体積が収縮します。純AIの温度と比容積(単位質量の物質が占める容積)の関係を示します。比容積は、溶融状態および固体状態で温度の低下とともに小さくなります。また、凝固時には液体から固体への相変態により大きく収縮(凝固収縮)します。凝固が完了すると熱収縮によって体積が室温に至るまで減少し続けます。この凝固完了後から室温に至までの熱収縮分を見込んで、鋳型や模型を作ることを縮み代といいます。
【まとめ】
凝固してから室温に冷却されるまでに鋳物は、熱収縮して寸法が小さくなります。それを見込んで、鋳型や模型を大きめに作ります。これを縮み代といい、収縮分を見込んだ目盛りをつけた伸び尺を使用します。
鋳物の設計5 削り代(けずりしろ)とは
削り代は、鋳物の機械加工のためにつける余分な部分をいいます。削り代、仕上げ代などとも呼ばれます。本来、鋳物は鋳肌のままで使用したいのですが、機械部品に取り付けたり、摺動部分として使用したりするために、鋳物の表面(黒皮といいます)の凹凸、粗い鋳肌、寸法不具合などを測りとることがあります。鋳造品の削り代は、JIS B 0403:1995「鋳造品ー寸法公差方式及び削り代方式」に規定されています。削り代を考慮した鋳放し鋳造品の基準寸法を示します。基準寸法は、仕上り寸法、さまざまな要因で発生する寸法のずれ、すなわち寸法公差、削り代で構成されます。
【まとめ】
鋳物を機械部品に取り付けたり摺動部品として使用したりするために機械仕上げをすることがあります。そのためには、あらかじめ削り代を設定して鋳物の寸法を決める必要があります。
引用参考文献:わかる! 使える! 鋳造入門 西 直美 (著)日刊工業新聞社
当社では、創業以来75年、様々なアルミ鋳物の設計・製造実績がございます。
お客様のご要望をお聞きした上で、最適な設計をご提案いたしますので、是非一度ご相談ください。